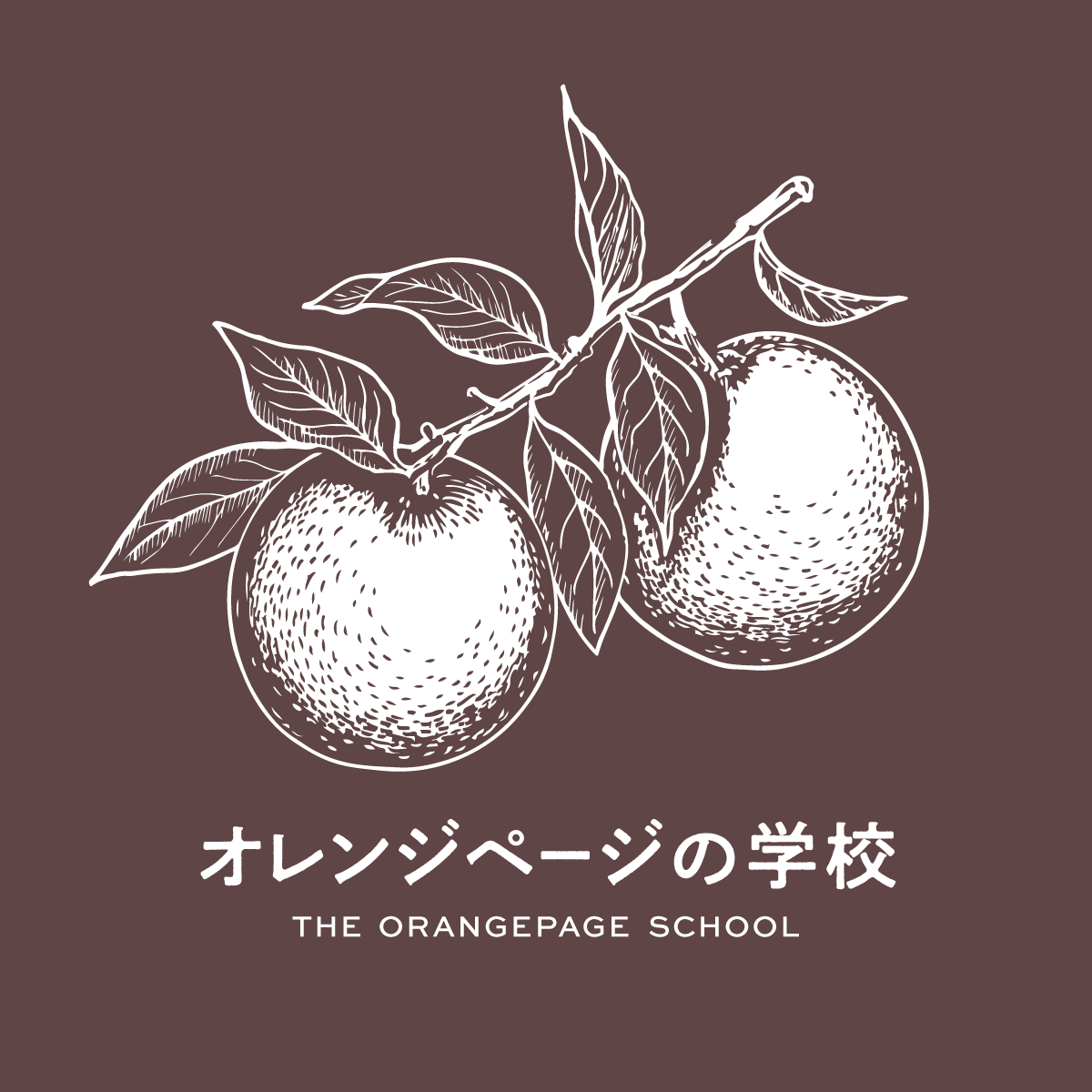日々の暮らしの中で、何気なく口にする「いただきます」という言葉。その背景にある“命をいただく”という行為を、真正面から見つめ直す人がいます。株式会社いにしえ代表・井形誠さん。広告代理店勤務から自然栽培農業の世界へ飛び込み、やがてワインや味噌といった発酵食品づくりへと歩みを進めた井形さんの軌跡には、食と生命を再接続するヒントが詰まっています。
「命をいただく」ことの重みから、すべては始まった

大学卒業後、広告代理店に入社し、営業職として働き始めた井形誠(いがた・まこと)さん。当時仙台で都市型のライフスタイルを送りながらも、休日や仕事終わりの時間を使ってボランティア活動に打ち込んでいました。
活動の内容は、交通事故に遭った動物の救護に駆けつけたりと、現場に根ざしたものでした。自然との関わりを肌で感じる中で、井形さんは徐々に「自然と共にある暮らし」に惹かれていきます。そんなある日、畑の作物を荒らす野生動物の存在に困っていた農家が、「殺してしまえばいい」とあっさり口にするのを聞いたとき、井形さんは言葉を失います。
「あれはすごくショックでした。もちろん農家の人たちが必死なのはわかるんですが、自然に生きてる存在を敵として排除する発想に、強い違和感があったんです。本来は人間も自然の一部のはずなのに、いつの間にか、人間 vs 自然っていう構図があたりまえになってしまってる。そこにすごく危うさを感じました」
この気づきは、井形さんの価値観を大きく揺さぶりました。自分がこれからどう生きるべきか、どんな働き方ができるのかという根源的な問いへとつながっていったのです。
食は自然との関係を映す鏡
この体験から井形さんは、人と自然、人と地球との関係、あり方について深く考えるようになったと言います。
「私たち人間って、もうずいぶん自然から離れてしまってると思うんです。本当は、複雑な自然のネットワークの中で、それぞれの命がバランスを取りながら生きているはずなのに、人間だけがその外に立って管理しようとしている。でも、農業や食って、もともとは自然と調和しながらやってきたこと。だから僕は、自然に手を加えるんじゃなくて、自然と一緒に在るという考え方に立ち返る必要があると思ったんです」
「命を大切にする文化を育てる」という思いのもと、「生き物と共存する農業」を見つけたい、そう思った井形さんは、それまでのキャリアを一旦リセットし、農業という未知の分野に足を踏み入れました。
転機となったのは、30歳のときに山形県の大規模農場で受けた農業研修。ここでは、早朝から日暮れまで、季節ごとの作業に追われながら土と向き合い、果樹の世話を学びました。
「そこは先進的な経営をする大規模な果樹園で、販売・通販の仕組みを学ぶことができました。研修先では農薬肥料を使っていたため、虫が少ないことに驚きました。農薬肥料を使わない果樹栽培の難しさも理解できましたが、自分でやる時は、もっと生き物が豊かに暮らす環境でやりたいと考えるようになりました」
自然栽培の果樹園から、商品づくりの構想へ

井形さんが目指したのは、より深く自然と向き合いながら「作る」ことに関われる環境でした。その舞台となったのが、山形県での果樹栽培です。かつて大規模農場で学んだ経験をもとに、2020年、仲間と共に自然栽培による果樹園づくりを始めました。
栽培するのは、ぶどう、りんご、桃といった土地に根差した果物たち。農薬も肥料も使わず、雑草や虫たちとも共生する畑での栽培は、まさに「自然まかせ」で、毎日が発見の連続でした。
「奇跡のリンゴ」木村秋則さんに学んだこと
井形さんが自然栽培に強く惹かれた背景には、「奇跡のリンゴ」で知られる木村秋則さんとの出会いがあります。きっかけは、青森県弘前市で開催された自然農法の勉強会でした。木村さんの畑をたずね、講演を聞く機会に恵まれたことで、その思想と実践に深く心を動かされました。
木村秋則さんは、10年以上もの歳月をかけて無農薬・無肥料のリンゴ栽培を実現させたことで知られる人物。農薬をやめた当初は一切の収穫がなく、周囲からも理解を得られず苦しんだ時期が続いたといいます。
「木村さんの畑に立ったとき、空気がまるで違ったんです。無農薬でりんごができるんだ、と確信できた光景を今も覚えています。無農薬なのに、普通にりんごがなっているという驚きと感動がありました」
木村秋則さんは、下草を伸ばし、茂らせたことでりんごの無農薬栽培の活路を見出した方。山の中の自然をヒントに、それを畑で再現するという考え方です。
「木村さんは、自然を徹底的に観察して、寄り添って、待って、信じて。その結果としてリンゴの木が自分の力を取り戻していったんです。農業って、育てるというよりも、本来の自然に寄り添った、育ちやすい環境づくりをすることなのかもしれないと思うようになりました」
「本当にいいもの」を求める声と向き合って
農業に軸足を置く一方で、井形さんは東京・自由が丘にあった自然栽培専門の青果店「自然栽培の仲間たち」で5年間、店舗責任者として勤務。お店の運営、飲食店などへの営業、イベント・セミナーの開催、自然栽培の普及活動を行いました。
「お客さんの中には、『これはどこで作られたんですか?』『農薬は使ってますか?』って、本当に細かく聞いてくる方が多かったんです。それって、不安だからこそなんですよね。価格や見た目じゃなくて、信頼できる食べものかどうかを知りたい。そういう声を毎日聞く中で、自分の中の価値観もどんどん動かされていきました」
一方で、そうした声に応える商品がまだまだ少ない現実にも直面します。「良いものを届けたくても、生産体制が追いつかない」「品質と流通の両立が難しい」そのジレンマを解決するには、市場のニーズを喚起し、一定の規模を持って取り組む農業経営が必要なのです。
「自然栽培に取り組む方の多くが、個人でスタートする方。農機具や施設などなかなか初期費用を捻出できる方がいない。だから小規模で割高の作物ができています。また、大きな流通に入り込めないから、販売のための活動にも大きな手間がかかる」
自然栽培を多くの方に知っていただくために井形さんが選んだ作物が、ワイン用のぶどうです。
「世界で最も研究されている果物であるぶどう。世界で最も価値の幅が大きく、もっとも飲まれているワイン。栽培によるぶどうの違いがワインの美味しさの違いになれば、自然栽培を一気に広められる、と思いました」
そう考えた井形さんは2020年に一家農園株式会社を立ち上げ、ぶどうの栽培とワインの醸造を開始しました。
ワインづくりが教えてくれた「素材の力」
一家農園で使用するのは自然栽培で育てたぶどうのみ。清澄剤や酸化防止剤、培養酵母などは一切使わず、酵母は果皮に付着する天然のものに任せ、発酵もぶどう自身の持つ力に委ねます。井形さんは、そうして生まれるワインをこう語ります。
「とにかく飲みやすい。やっぱり自分のワインが好きだからかもしれないけど、体が欲しがっているかのようにスーッと染み込んで消える感覚がある。畑で生き物たちの元気を受け取って、生き生きと育ったからなのかな、と思っています」
素材が良ければ、複雑な工程や添加物に頼らなくても、その土地と人に根ざした味わいが生まれます。逆に、素材の持つ力を削いでしまう加工がいかに多いかを、ワイン造りが教えてくれたのです。
「伝統を継ぎ、未来を仕込む」味噌に込めた思想

自然と調和しながら命をいただく。そうした思想を深めた井形さんが次に向き合ったのが、発酵食品の代表格「味噌」でした。
「青果店で接したお客さまに『せめてお米とお味噌だけでも良いものを選びたい』って言われたんです。その言葉がすごく印象に残っていて。味噌は日本の食文化の中心ですし、毎日食べるもの。地域ごとに特性があるし、体にも良く、薬に代わる食といえる代表格。お味噌文化に遺された、地域の自然と健康の叡智を現代に生かし、次の世代に繋げるためにもやってみよう、と思いました」
地域の味噌は文化の地層
味噌は、地域によって使う大豆や麹、塩が違い、蔵の菌や気候が味に独自の個性を与えます。
「味噌蔵の方々とたくさんお会いしてお話を聞くなかで、何度も出てきたのが、昔の麹屋さんの風景なんです。『うちはもともと麹屋だったんです。みんな、自分の家で育てた大豆を持ってきてね。それを茹でて、うちの麹と塩を混ぜて、味噌に仕込んで返してあげる。それをお家で発酵させて、各家庭でお味噌を完成させていたんですよ』って。こういう文化を、僕たちの手でもう一度、次の世代につないでいきたいと思うようになりました」
味噌の原材料にこだわることは、日本の農業の未来にもつながると井形さんは考えています。現在、味噌の原料である大豆の多くは輸入品。そこに風穴を開けるべく、いにしえでは各地の在来種の大豆や米、海塩を使った、その地域の文化に沿った味噌づくりに取り組んでいます。
「たとえば山形なら『秘伝豆』とか『里のほほえみ』とか。それぞれの豆は、その地に適応して、育ちやすく美味しくなることから盛んに作られるようになっています。その個性をいかした特産品としての味噌も、他の地域では真似できないものになります」
手間と時間が生み出す、生きた味噌
いにしえが味噌づくりにおいて大切にしているのが、地域の蔵元との協働です。例えば、山形県米沢市にある今野味噌醤油醸造所では、130年以上続く天然醸造の技術が今も受け継がれています。加温せず、ゆっくりと熟成を待つ。その工程には、効率とは真逆の「時間と対話」が存在します。
「今の時代って、どうしてもスピードとコストが優先されがちだけど、味噌って逆なんです。ゆっくり、菌の声を聞きながら仕込む。そのプロセスにこそ、手仕事の尊さがあると思うし、だからこそ本当に生きた味が生まれる。蔵元さんたちの技と、僕たちの素材と思想が出会うことで、新しいけれど、どこか懐かしい味噌ができるんです」
現在、いにしえが手がけている味噌には、たとえば山形の「いろは味噌」や新潟の「にいがた味噌」があります。
「いろは味噌」では、つや姫やひとめぼれなどの自然栽培米を用いた米麹と、地元産の秘伝豆やエンレイなどの在来大豆を使用し、宮城県産の伊達の旨塩で仕込んでいます。一方の「にいがた味噌」は、新潟の酒米・五百万石の麹と、甘みの強い大豆「さといらず」を用い、日本海の塩を合わせた一本。
どちらも非加熱・無添加で、6か月以上の天然熟成を経て、素材と地域の個性がそのまま味に表れています(現在は2年熟成を販売中)。いにしえの味噌は、単なる調味料ではなく、「生きた文化そのもの」であると言えるでしょう。
食は、薬に代わる
井形さんの味噌づくりに込められたこだわりは、単に「おいしさ」や「文化の継承」にとどまりません。その背景には、より根源的な視点「食は健康を支える力を持っている」という確信があります。言い換えれば、「薬に代わる食」という信念です。
添加物、保存料、農薬。現代の食の現場ではあたりまえに使われているものですが、これらを「使わない」という選択肢を世の中に提供することには大きな意義があると井形さんは考えています。
無添加・生味噌のもつ「生きた力」
いにしえの味噌は、加熱殺菌を行わない生味噌。これは、発酵菌や酵母などの微生物が生きたまま味噌の中に存在しているということ。発酵が生きていることで、味噌は単なる調味料ではなく、腸内環境を整え、免疫を助ける生きた食品になります。
「やっぱり、生きてるって大事だと思うんです。火を通してしまえば保存しやすいけど、菌の力は止まってしまう。毎日食べるものだからこそ、体にちゃんと作用するものを届けたいと思いました」
素材として使われる米や大豆はすべて自然栽培。農薬も化学肥料も使わず、土の力、気候の力、生きものの営みに委ねて育てた作物です。こうした素材は、味噌として発酵したときにも生きた菌の活動を妨げず、自然なかたちで体に入っていきます。
「栄養って、ただ成分が入っていればいいってものじゃないと思うんです。体がちゃんと受け取れるかどうかが大事。だからこそ、素材の育て方にも責任を持ちたい。結果として、腸や心の健康にもつながっていくと信じています」
食べることは、生き方の選択
いにしえの食品づくりは、ただ健康にいいものを提供することが目的ではありません。井形さんが伝えたいのは、「何を食べるか」は「どう生きるか」という問いと地続きであるということです。
「スーパーに並ぶものを何気なく選ぶ。それって日常的な行為だけど、実はすごく大事な選択なんですよね。『この食べものは誰がどこでどうやって作ったのか』ここに意識を向けるだけで、自分と自然とのつながりも見えてくる。そういう食のあり方を広げたいんです」
井形さんの言葉のひとつひとつには、「食」を通して命を守り、自然と調和する社会をつくりたいという静かな情熱が込められています。味噌という伝統食品に宿る“生きた力”を信じ、未来に手渡そうとする井形さんの姿勢。そのひたむきな実践の中にこそ、現代の食を見つめ直すヒントがありそうです。
「おいしい」の向こう側へ

おいしいものを作る。それは、食品に関わる誰もが目指す当たり前のゴールかもしれません。でも井形さんは、そこから一歩踏み込んだ問いを投げかけます。
「見た目や香り、味のバランスだけで、おいしさを語ってしまうと、素材がどう育ったか、誰がどう作ったかという背景が見えなくなってしまう。僕たちは、その背景を大切にしたいんです
味噌で日本の大豆自給率を変える
現在、日本で使われている味噌の多くは、原料となる大豆を海外からの輸入に頼っています。いにしえではこの状況に対して、自然栽培による国産大豆を使用し、できる限り顔の見える素材を調達する体制を構築しています。
「味噌って、日本の食卓に欠かせない食文化なのに、原料がほとんど外国産というのはやっぱり違和感があって。地域と密接に繋がっているものなので、近くの土地から生まれてきた作物であることや、健康な土地で健康的に育てられたものこそ、普段食べるものにしたい。そこまで踏み込んでようやく、おいしさの本質に近づけると思うんです」
味噌という身近な食品を通じて、自給率の問題や農の現場と向き合い、そのあり方を問い直す。いにしえの挑戦は、単なる企業活動を超えた、社会全体へのメッセージにもなっています。
いにしえの農業には、「排除しない」という姿勢が貫かれています。雑草も虫も、自然の一部。人間の都合だけで環境を整えるのではなく、あらゆる命を「共にあるもの」として受け入れる農のあり方を追求しています。
「雑草や虫を敵にせず、共存する農業を行うことで、たとえば味噌に使う豆が持つ甘みや香りが、より際立つようになる。もちろん収穫までに時間はかかるし、収量も安定しないかもしれない。でもそれは、自然との関係性をもう一度見直すきっかけになります。私たちが自然に近づき、自然のリズムに寄り添った食のあり方を広くめたいと考えています」
いにしえの活動は、単に食品を作って届けることにとどまりません。「食べる」ことの背景にある構造、命の循環、環境への配慮、文化の継承。そうしたすべてを含んだ“食のデザイン”を見直すための、小さな革命だと言えます。
「水とミネラル以外、私たちが口にする食べ物は、生きものです。つまり、私たちは生きるために、他の命をいただいているのです。だから『いただきます』という言葉には『私が生きるために、あなたの命を、いただきます』という感謝と敬意が込められています。だからこそ、いただかない命が守られる農業を営んでいます」
井形さんが目指す農業は、あらゆる生きものたちの命を大切にすればするほど、美味しい作物を得られる、そんなありかたの農業なのです。
クリエイター
広告代理店業務の傍ら野生動物保護のボランティア活動に関わる中で、自然との共生や人と命の関係に深い関心を抱くようになり、自然栽培の果樹園を立ち上げる。2021年、株式会社ネークル(現・いにしえ)を創業。ナチュラルワインの製造や非加熱・無添加の「いにしえ味噌」などの開発を通じ、人・自然・文化をつなぐ食のあり方を追求している。
「オレンジページの学校」編集部など、株式会社オレンジページの中の人です。みなさまのお役に立てるよう張り切って運営しています。よろしくお願いします。