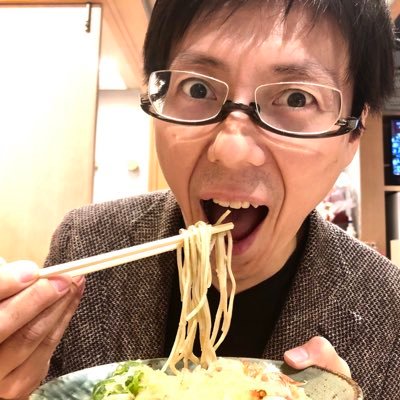福井県で古くから伝わる「越前そば」を愛し、いままで数多くのそば屋を訪問。そば愛好家の奥村慎爾(しんじ)さんに、「越前そば」の魅力について伺いました。その偏愛ぶりは、歴史的文化遺産の「そば皿」の復刻まで着手してしまうほど……! 多岐に渡る“そば活”について、たっぷりお話を伺いました。
目次
- 目次
- 「そば通」ではなく「そば好き」なんです
- そば好きは伝染する?
- おいしいそばができる条件
- 「越前そば」あれこれ
- 愛して止まない「そば活」秘話
- 麺をすするだけじゃない! そばの実レシピ
「そば通」ではなく「そば好き」なんです
「福井のそばが好きすぎて毎日そばを食べている、ただの変態です」。奥村慎爾(しんじ)さんのSNS投稿の紹介文には、そんなフレーズからはじまります。

ご本人自ら変態を語り、365日、毎日そばを食べ続けた男としてNHK放送のテレビ番組にも出演。2022年1月16日から2024年12月4日まで、毎日そばを食べる活動をスタート。SNSに投稿もされていました。


そば屋の食べ歩きは、じつに開始2年間で約180軒を超えるというのですから驚異的です。
自称「そば好き」と謙遜される理由を聞いてみると……。
「そば通のかたは、正しい食べ方の指南ができる正統派なイメージですが、私の場合はむずかしいことは抜きにして『おいしく食べればいいじゃないか』、というラフな立ち位置だと思っていて。広くそばの多様性を楽しんでいる感じです」
いまでも年間で約100軒ほど、多い日には1日2~3軒のそば屋ののれんをくぐることがあるという奥村慎爾さん。そこまで“そばのとりこ”になったきっかけは何だったのでしょうか。


そば好きは伝染する?
その出会いは、いまから20年以上前。当時、奥村慎爾さんがグラフィックデザインの会社に勤めていたころのこと。
「2004年に、テレビ局のFBC福井放送さんから“そばびと”という、福井県内のそばに関わる人を紹介するお仕事の依頼がありました。撮影スタッフさんと、地元のそば屋を取材しながら食べ歩いたんです。
それまでは、そば屋では普通の麺状のものしか食べたことがなかったのですが、ある店主にすすめられて、初めてそばがき(そば粉を熱湯でこねて餅状にしたもの)を食べてみたんです。そしたら、そのあまりのおいしさにビックリしてしまって!」
福井県産そば粉100%を使用したそばがきを食べた瞬間。そばの実の野性味あふれる豊かな香りと、独特の甘みに魅了されてしまったそう。
「当時私はまだ20代で、スタッフも同世代。若い世代のみんなで、そばってこんなにおいしいものなんだ!と、すっかりハマってしまったんです」

そばのおいしさとともに感動的だったのは、店主の実直さにもあったとか。
「どの店の店主も手間を惜しまずに、そばに愛情をかけているのが伝わってきました」
そば屋を営む店主のインタビューを重ねていくうちに、そば愛がどんどん増していったそう。最初は、仕事からはじまったライスワーク(食べていくために稼ぐ仕事)でしたが、そばの魅力を伝える仕事は、いつしかライフワーク(人生を捧げた活動)へ。奥村さんにとっては自然の流れだったのかもしれません。

おいしいそばができる条件
福井の「越前そば」には、大きく3つのこだわりがあるといいます。
「一番は、在来種のそばの実をずっと守ってきたところですかね」と奥村慎爾さん。在来種とは、その土地に古くから存在してきた生物種のこと。
「そばの名産地といわれる地域でも、在来種ではなく品種改良されたそばの実を使って、そば粉にしているところがほとんどです。品種改良することで、収穫量を上げて安定的に収穫できるという利点があります。
そばの実は黒く完熟させてから収穫するほうがラクなので、一斉に黒くさせて黒化率を上げることができます。福井は、品種改良を一切していないので、黒い実やまだ若い緑色の実が混ざっている。それが、かえって豊かな味のグラデーションになっているようです」
越前そばの王道は「おろしそば」。おろしろばとは、黒っぽくてやや太めの田舎そばに、薬味の大根おろし、ネギ、かつお節をのせ、ダシをぶっかけて食べる、福井県のソウルフード。さっぱりとした味わいで、大根おろしやダシ、具などにも様々なバリエーションがあるのも特徴です。
(参考文献:福井市観光公式サイト「福いろ」)




福井県民が品種改良をしなかった理由は、「味が落ちるから」。答えはとてもシンプルでした。
「品種改良したほうが生産者の労力は軽くなりますが、それをしてこなかった。先人たちの“そば愛”で在来種を守り抜いてきたことを誇りに思いますね」
2つ目は、「製粉技術のよさ」です。
「通常、そばの実を収穫してからの製粉工程は、『ロール製粉』と呼ばれる方法でそば粉にする方法がありますが、福井のそば屋は、石臼で製粉するのが一般的。もともと、小和清水(こわしょうず)と呼ばれる石臼に使用される、石の生産地だったみたいですね」
石臼で製粉するほうがそば粉を作るうえで余計な熱がかからないため、上質で繊細な仕上がりのそば粉が作れるといわれているとか。
3つ目は、名水が流れている風土にあるといいます。
「例えば、私が住んでいる大野市の住宅の約7~8割が地下水を使っています。市内には名水百選にも選ばれた湧水もあり、大野市の水はおいしいな、と感じます。ほかの市町にあるおそば屋さんでも、わざわざ遠く離れた湧水を使っているところもあって。そういった良質な水が身近にあることも、そばがおいしいと言われる理由の一つかもれませんね」
古来から大切に継承されてきた「越前そば」ですが、特に有名なのは、冷たいそばに大根おろしがたっぷり盛られた「越前おろしそば」です。

「この食べ方は、1601年に府中(現在の越前市)の領主としてやってきた本多富正(ほんだ とみまさ)が、京都・伏見から蕎麦職人をつれてきたことから生まれた、というのが福井県内では定説になっています」
さらに、健康面でもプラスになるよう、城下の医者と相談し、大根おろしと一緒に食べることができるそばメニューを考案したのが、「越前おろしそば」の由来だそう(※)。
「越前そば」あれこれ
クリエイター
1978年、大阪府生まれ。小学生のころから父親の地元である福井県で育つ。高校卒業後はグラフィックデザイン会社にて就職。キャリアを積んだのちに独立し、フリーランスへ。現在は、福井県大野市在住でデザインやコンサル業の傍ら、福井県の「越前そば」にまつわる情報や食文化の発信に尽力を重ねている。
「ヒトは食べたもので体がつくられる」をモットーに“食と健康”をライフワークとする。日本の食文化に関心が高く、著書に『おにぎり~47都道府県のおにぎりと、米文化のはなし~』(グラフィック社刊)がある。管理栄養士としての執筆活動にも力を注いでいる。